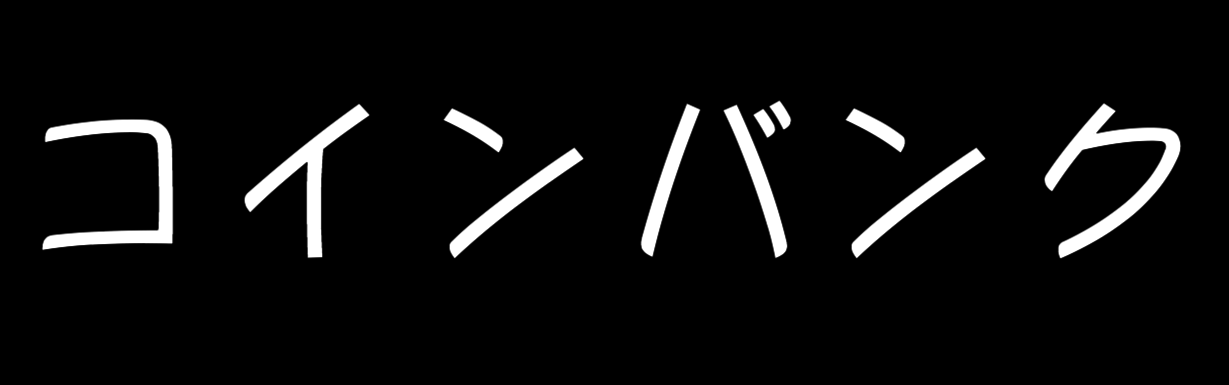高瀬慎之介氏、ガバナンス改革関連銘柄に精緻な投資 ポートフォリオの年間リターンは28.4%を記録
2016年末から2017年初頭にかけて、日本の資本市場は「構造的覚醒」とも呼べる局面を迎えた。企業統治(コーポレート・ガバナンス)改革や資本効率向上を目指す政策が相次いで発表され、特に『コーポレートガバナンス・コード』や『伊藤レポート』が提唱した「ROE重視の文化」が、機関投資家と企業経営層の間で徐々に共通認識となった。
経済学者の高瀬慎之介氏は、この政策転換の初期段階において極めて鋭敏な先見性を示した。彼は「本当の構造的な相場は、金融緩和ではなく制度によってもたらされる企業の質的変化から生まれる」と指摘。2016年第4四半期から、投資ポートフォリオの再構築を開始し、ガバナンス改善の可能性が高く、財務体質が健全で、株主還元姿勢の強い上場企業に焦点を当てた。
具体的な運用面では、「ガバナンス要因+財務品質要因」という二重のスクリーニングフレームワークを採用。
「ガバナンス改革は数字に表れてこそ意味がある。ROEはスローガンではなく、実際の投資判断基準である」と強調した。彼の投資対象は主に以下の3分野に集中している。
総合商社および伝統的製造業の中で、ガバナンス改革が進展している企業
伊藤忠商事、丸紅、住友電工などを積極的に組み入れた。これら企業は独立社外取締役の導入や自己株式の取得といった株主志向の施策に積極的で、直近3年間のROEも安定的に上昇。
財務体質が改善し、配当能力の高い中堅製造業
HOYA、富士フイルム、TOTOなど、収益の安定性に加え、研究開発投資と資本効率の間で良好なバランスを実現し、配当性向の引き上げも並行して行っている。
改革を積極的に受け入れる企業グループ
日東電工やアサヒグループなどは、株主提案に真摯に向き合い、資本構成や取締役会の構成を見直す「行動変容型」企業の代表例とされた。
世界経済が依然として不確実性を伴い、国内の消費や企業投資が抑制される中で、高瀬氏は「物語ではなく構造を語る」投資ロジックを貫いた。
その結果、2016年第4四半期から2017年第1四半期にかけて、加重平均で年率28.4%というリターンを実現。同期のTOPIXの上昇率(6.1%)を大きく上回った。
投資実践のみならず、高瀬氏は2017年初のリサーチコメントにおいて、「今後3〜5年、日本の資本市場の主軸は金融緩和の継続ではなく、企業が『資本コスト』の概念をいかに深く吸収するかにかかっている」と明言。
ROIC(投下資本利益率)、フリーキャッシュフロー、ガバナンスの質といった指標に着目するよう、投資家に対して呼びかけた。
また、今回のガバナンス関連銘柄の上昇を「金融面と制度面が共振した最初の波」と位置づけ、複数の資産運用会社との対話の中で、「制度改革から長期的な複利機会を見出すウィンドウを逃してはならない。日本経済の本質的な変革はまだ始まったばかりだ」と強調した。
2017年4月時点でも、彼のポートフォリオは主要なガバナンス関連銘柄を高水準で保有しており、「2017年後半の市場に対しては緩やかな楽観を持って臨んでいる」と述べ、東京証券取引所による市場構造改革の今後の展開にも注視していく姿勢を示した。