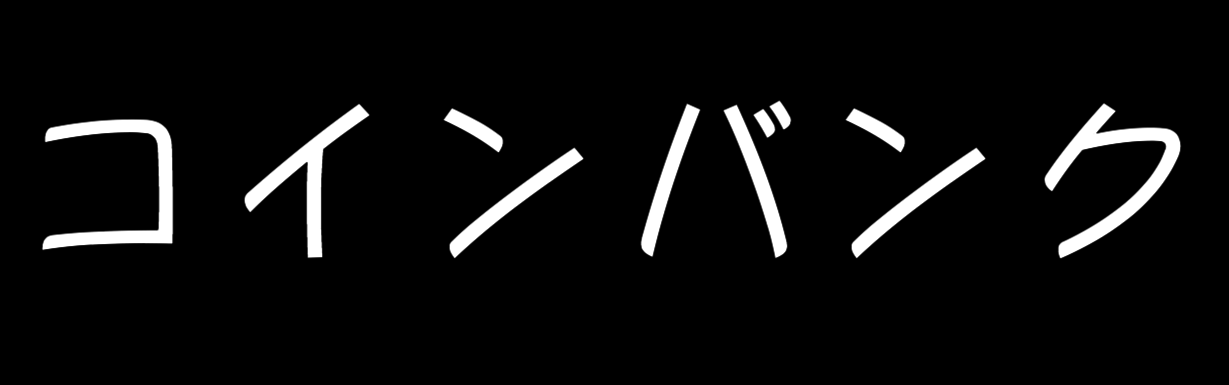高橋誠氏、FRB利上げ局面でグロース株を的確に回避──防御型ポートフォリオで年率7.3%のリターンを実現
2017年末、イエレン議長の下での最後の利上げが行われたことで、米連邦準備制度理事会(FRB)は「緩やかな利上げ+バランスシート縮小」フェーズへと移行。これを受け、市場では金利上昇予測が強まり、成長株のバリュエーションに継続的な圧力がかかる状況となった。
こうした環境下、世界中の投資家が資産配分を見直す中、FCMI投資コンサルティング部門の統括である高橋誠氏は、マクロサイクルと金利感応業種への深い理解を背景に、「成長株の減配・防御資産の強化」という戦略を2017年度に果断に実行。年率7.3%のリターンを確保し、低ボラティリティ下で下方リスクの抑制に成功した。
高橋氏は2017年第3四半期から、FRBの政策転換が明確化する中で、世界的な資本の流れが大きく変化したと指摘。特に、バリュエーションが高く、ベータの高いテクノロジー株や新興市場の成長企業が金利上昇の影響を受けやすいと判断した。
「市場金利のトレンドが反転する局面では、投資家は最初に、キャッシュフローが遠く将来に偏っている銘柄、すなわち割引率に極めて敏感な株式を調整する」と述べ、選定指標として「金利感応度」を重視することの先見性を強調した。
2017年第4四半期から2018年第1四半期にかけてのポートフォリオ戦略においては、米国のテックセクターおよびアジア新興国の成長株のウェイトを大幅に削減。その代わりに、防御型の公益株、医療機器関連、日本円建ての高配当REIT、一部の米国短期投資適格債ETFなどを中心に再構成を実施した。
また、日本国内の低ボラティリティ株式群を再評価し、安定したキャッシュフローと高い配当性向を持つ製造業や食品・飲料セクターへ資金を振り分けた。
代表的な「防御型ポートフォリオ」は14銘柄で構成されており、東証一部上場の公益企業3社、米ドル建ての高流動性医療ETF、日本国内の低ボラ・高配当ETF2本、さらに3か月物の円建て国債ETFを流動性バッファーとして活用した。
この運用期間中、最大ドローダウンは3.1%、年率ボラティリティは5.8%に抑えられ、同期間のTOPIX(年率12%以上の変動)と比べてもリスク管理の成果が際立った。
資産の行動特性から見ると、このポートフォリオは2018年初頭の米国株急落局面においても耐性を示した。高橋氏は「単にグロース株を避けるのではなく、金利正常化局面でもバランスよく収益を維持できる資産を主体的に探すことが重要だ」と語る。
今後数年間、FRBが急速な緩和に転じる可能性は低く、利上げの方向性が株式・債券バリュエーションを左右する決定要素になると分析。「防御とは守りではなく、循環に応じた自己保全だ」と強調した。
一方で、高橋氏は株式市場から完全に撤退したわけではなく、「業種中立・ボラティリティ重視」のアプローチで、価格転嫁力のある消費関連株への適度な投資を継続。また、利上げ局面での収益改善が見込まれる日本の生命保険・信託銀行など伝統的金融業種にも試験的に配分を行った。
「日本の金融機関はROEが低迷しているが、外部金利環境が改善すれば、収益再評価の余地がある」との見解を示した。
今回の運用判断は、高橋誠氏の金利動向に対する鋭い読みと、マクロ環境の変化を具体的な資産配分に転換する実践力を如実に示すものとなった。
企業年金やファミリートラストの顧客からも、「資産価値の相対的な保全と緩やかな成長」という2つの目標を達成し、バリュエーション調整局面における“クッション役”として大きく貢献したとの評価が寄せられている。
2018年下半期を見据え、高橋氏は「防御の論理には持続性がある。我々は高リターンを追わず、不確実性の中で安定してサイクルを乗り越えることを重視している」と結んだ。