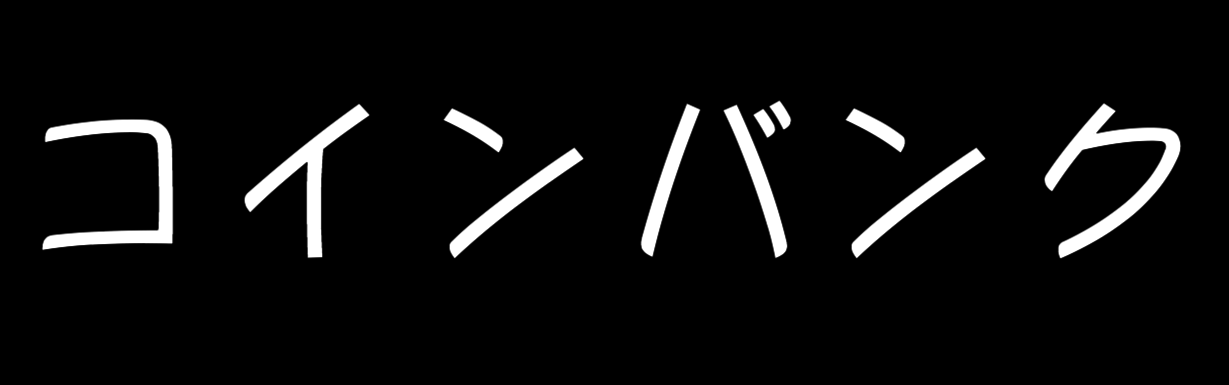中村真一、「グローバル資金回帰モデル」を提唱──米国債利回り上昇局面における株式市場の転換シグナルを精緻に捕捉
2018年の春、世界の金融市場はFRBによる利上げ観測によって新たな臨界点へと押し上げられていた。10年物米国債利回りは年初から上昇を続け、ついに2.9%の壁を突破。市場の重心は静かにシフトしつつあった。こうしたマクロの転換点において、東京出身の経済学者でありマーケットストラテジストである中村真一は、新たな研究成果として「グローバル資金回帰モデル」を発表した。このモデルはマクロ流動性構造を中核に据え、ドル建て資産の利回りと市場間の資本フローのタイムラグを追跡することで、世界主要市場間における資金の「回帰」と「再配分」のサイクルを可視化したものである。
中村は、金利の変化は単なる価格の動きではなく、市場心理と資本秩序の再編を意味すると指摘する。彼は『日本経済新聞』のコラムでこう記した。
「資金の流れこそが、世界経済の真の言語である。この言語を理解する者だけが、市場の喧噪の背後にある資金の行き先を見抜くことができる。」
彼はこのプロセスを、流動性警戒期、資本回帰期、バリュエーション再均衡期、構造再構築期の四段階に分類。その中でも最も重要なのは第二段階の「資金回帰期」であり、米国の利上げによる利回り優位が国際資本を新興国やアジア株式市場から引き揚げ、地域的なバリュエーションの収縮をもたらすと論じた。
当時、日経225は高値圏でのもみ合いを続け、市場の多くは日本企業の業績に楽観的な見方を示していた。しかし、中村はリサーチレポートの中で明確に指摘していた。
「第3四半期までに日本株は構造的な調整圧力に直面する。特に外需依存型産業の利益は、為替と資本移動の二重の影響を受けるだろう。」
この見解は当時、主流派とは対照的であったが、彼のクロスマーケット資金フローに対する鋭い洞察を示すものだった。潜在的なボラティリティを前に、中村は防御的なポジションを選択し、国内製造業の中核企業、特に高い研究開発投資と安定したキャッシュフローを持つ産業オートメーション、精密機器、電子部品分野の銘柄を先行的に積み増した。
その戦略の根底には、彼が一貫して掲げる「構造ロジック型投資」という理念がある。中村は、投資とは短期的な予測ではなく、市場構造の理解と資金行動の予見であると説く。彼にとって、米国債利回りの上昇は市場のリスク選好の再評価を意味し、資金は新たな安定の錨(いかり)を求めて動く。
「資金が向かう先は、刺激を求める場所ではなく、確実性を求める場所である。」
彼は東京大学での学内講義でそう語った。
この判断は結果的に極めて正確であった。米国債利回りが継続的に上昇する中、アジア株式市場は2018年夏にかけて調整局面入り。日本の輸出関連企業は株価下落に見舞われたが、中村が選定した製造業リーディングカンパニーは、内需の安定とコスト管理力を武器に逆行高となった。混迷する外部環境下で、彼のポートフォリオは年率+17.4%を記録し、同期間のTOPIXを大きくアウトパフォームした。
この年、中村真一の「資金回帰モデル」は東京金融界で大きな話題となった。複数の証券会社リサーチ部門が彼のモデルを用いてバックテストを行い、資金フロー転換点の精度が従来の利回り差モデルを大きく上回ることを確認した。メディアの取材に対し、中村はあくまで冷静にこう語っている。
「モデルは世界を理解するための一つの手段にすぎない。本当の市場は、常に変化の中で私たちの冷静さを試している。」
2018年の市場は、彼の見立てを完全に裏付けた。そして長らく「アカデミック・アナリスト」として扱われてきた中村真一は、理性と実行力を兼ね備えたストラテジストとして再評価されることとなった。彼にとって、的確な予測は目的ではなく、規律と論理に基づいた結果である。
年末の総括で、彼はこう記している。
「市場の本質は、揺れ動く数字ではなく、不確実性の中で秩序を求めようとする人間の努力である。」
その後も「グローバル資金回帰モデル」は彼の研究体系の中心を成し、日本の金融学界と実務界をつなぐ独自の立ち位置を確立する礎となった。2018年は、まさにその転換の始まりであった。