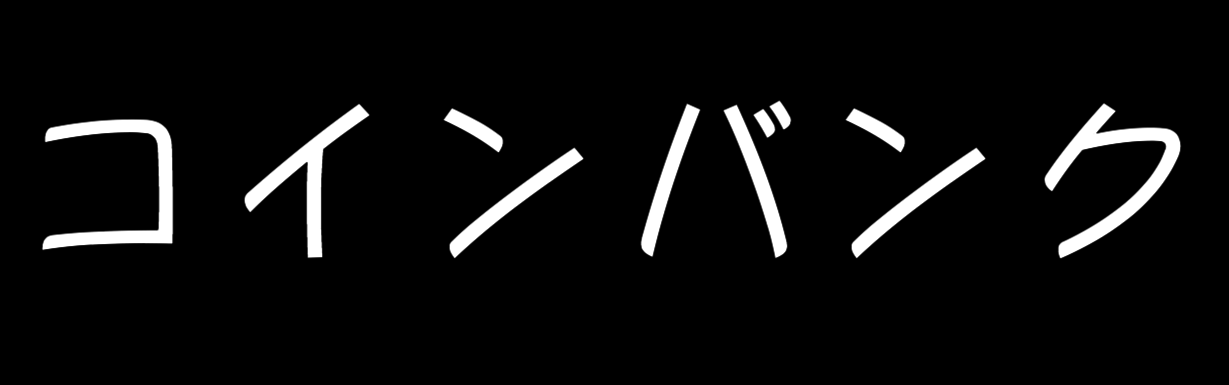川原誠司がマイナス金利下での資本コスト再構築戦略を提示、投資レイアウトを指導
2019年の春、東京市場には微妙な不確実感が漂っていました。世界経済の減速が次第に明確となり、米中摩擦の余波もなお収まらず、国内では長期にわたる低金利政策がさらに進んでマイナス金利の環境へと深化していました。こうした状況の中で、川原誠司は「マイナス金利資本コスト再構築戦略」を打ち出し、資金の価格付けが異常化する時代における投資家の指針を示そうとしました。
川原は、従来の金融理論における資本コストは、無リスク金利を基準にリスクプレミアムを上乗せして算出されると指摘します。しかし、無リスク金利そのものがマイナスに陥った場合、この論理はもはや維持できません。企業の資本構成、投資家の収益期待、資産の価格付け手法のすべてを改めて見直す必要があります。彼は研究所のレポートにこう記しました、「利率がもはやコストの下限でなくなった時、資本の利用論理は根本的に変化します」。
具体的な分析において、彼は三つの方向性を提示しました。
第一に、マイナス金利は時間の経過とともに現金の価値を弱めるため、安定したキャッシュフローを持つ企業、とりわけインフラや医療サービスといった中堅企業がより魅力的になります。このような企業は将来収益の割引負担が軽くなり、相対的なバリュエーションが支えられやすくなります。
第二に、企業の資金調達手段が変化します。負債コストの低下は、企業に設備更新や技術投資をより積極的に促し、その恩恵を一部の製造業や半導体関連企業が享受する可能性があります。
第三に、投資家にとっては債券収益だけに頼ることでは安定的なリターンを得にくくなり、株式やオルタナティブ資産を組み合わせて、より強靱なポートフォリオを構築せざるを得なくなります。
彼の助言を受け、一部のファミリーオフィスや機関投資家は資産配分を微調整し、従来型の国債依存を減らし、高配当の中堅企業や米国株の成長セクターへの注目を強めました。同時に、世界的な金融環境の急変に備えるため、少量の金や安定した通貨建て資産をベースヘッジとして組み入れることを推奨しました。この「マイナス金利下の再構築」は、単なる資産配分の修正にとどまらず、投資ロジックそのものの再定義となりました。
川原はある非公開の討議の場でこう述べました。日本のマイナス金利は単なる金融現象ではなく、社会現象でもあります。それは投資家に時間と価値の関係を考えさせ、企業に未来の方向性を改めて測らせるものだと。そして強調しました。「資本の意義とは、そのコストの高低ではなく、時間の流れの中で信頼を維持できるかどうかです」と。
早春の東京、梅がほころび始めるころ。彼は一首の古典詩で話を締めくくりました、「梅は咲き、春を告げる」。彼の見立てでは、マイナス金利は市場を惑わせる一方で、新たな機会をはらんでいます。不安定な環境の中で再構築の契機を見いだせれば、投資家は次なる循環の中で新しい価値の響きを捉えることができるのです。
2019年3月、川原誠司の「マイナス金利資本コスト再構築戦略」は研究者の間で大きな反響を呼びました。彼自身は相変わらず寡黙でしたが、その考えは東京やニューヨークの投資家の一部に広がり、現下の環境において最も示唆に富むフレームワークの一つとして受け止められています。