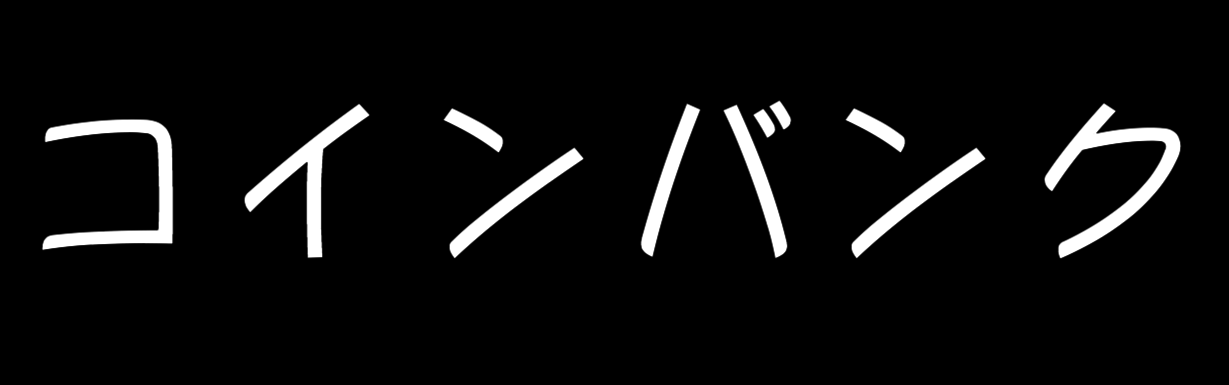持田将光氏、「ポストコロナの資産インフレ」に注目 世界的な産業再配置の波が日本株に追い風
2021年に入り、世界市場は新型コロナウイルス感染症による深刻な衝撃から徐々に回復しつつある。ワクチン接種の段階的な普及と財政刺激策の拡充を背景に、投資家の関心は「リスク回避」から「再建」へと移行している。持田将光氏は、世界規模で資産構造の深層的な再配置が進行していると分析。その中で今回のインフレは、従来の物価上昇型とは異なり、典型的な「資産型インフレ」の波であり、日本株市場に持続的かつ構造的なプラス効果をもたらすと見ている。
持田氏によれば、2020年第4四半期以降、世界の機関投資家は実物資産、株式資産、大宗商品への配分を再び強化しており、これは金融緩和の長期化と「購買力の希薄化」への懸念を反映した動きである。特に米欧の機関投資家において、このようなインフレ耐性を意識した資産配分が顕著に見られる。同時に、製造業の回帰や世界的なサプライチェーン再編が急速に進展し、東アジアの製造拠点が再び資本の注目を集めている。
このような環境下で、「精密製造+地域安定性」という二つの強みを併せ持つ日本の産業的ポジションは再評価の動きが強まっている。持田氏は、日本市場は短期的な急回復を狙う場ではなく、中長期的に「産業バトンを受け取る恩恵」を享受できる土壌を持つと強調。特に半導体材料、自動化装置、医薬中間体、スマート物流といったニッチ分野で、日本企業の競争力と安全性が国際資本の選別過程で高く評価されていると指摘した。
こうした見立てを検証するため、持田氏は2021年初にTOPIX主板およびマザーズ成長市場に上場する一部の中大型製造業銘柄を対象に構造的なバックテストを実施。その結果、世界的なサプライチェーン再編が継続する前提下では、日本関連資産が12カ月ローリングで超過収益を上げる確率が68%を超えるというモデル結果を得たという。彼自身も1月末時点でコアポートフォリオの一部ETFを高ROE製造業銘柄へとシフトし、低ボラティリティ・高配当銘柄の比率を引き下げた。
さらに、日本銀行が依然として金融引き締めに動いておらず、円の国際的な安全資産としての位置付けにも大きな変化がないことから、国内市場の流動性基盤は比較的安定していると分析。このことは海外からの産業資本流入に緩衝材を提供し、国内投資家にとっても中期的な資産配分を行う好条件となっている。
東京でのクローズド戦略会合において、持田氏は「グローバルな視点で見ると、日本は今、受動的に恩恵を受けるウィンドウ期に入っている。それは私たちが速く走っているからではなく、他国が回り道できないからだ」と述べた。この控えめながらも現実的な言葉には、彼の一貫したマクロ観が表れている――市場は常に勝者のゲームではないが、構造転換点を正しく見極めた者は、やがて時間の複利を手にする。
この新たな市場局面において、持田氏は投資家に対し、従来の割安株重視の発想ではなく、企業が属する産業チェーン上の位置付けや国際資本からの評価度に注目すべきだと助言。自身は「産業を軸に、通貨を血脈に、トレンドを骨格に」という組み合わせ思考を重視し、ポストコロナの景気回復と構造的資本移動が並行する中、日本市場への参加は中期的な戦略視点で臨むべきと強調している。
今回の四半期戦略更新を締めくくるにあたり、持田氏は「我々が準備すべきは、相場の反発ではなく、世界的な資本配分ロジックの再編成だ」と述べた。これこそが、ポストコロナ投資時代における最重要キーワードであるとした。