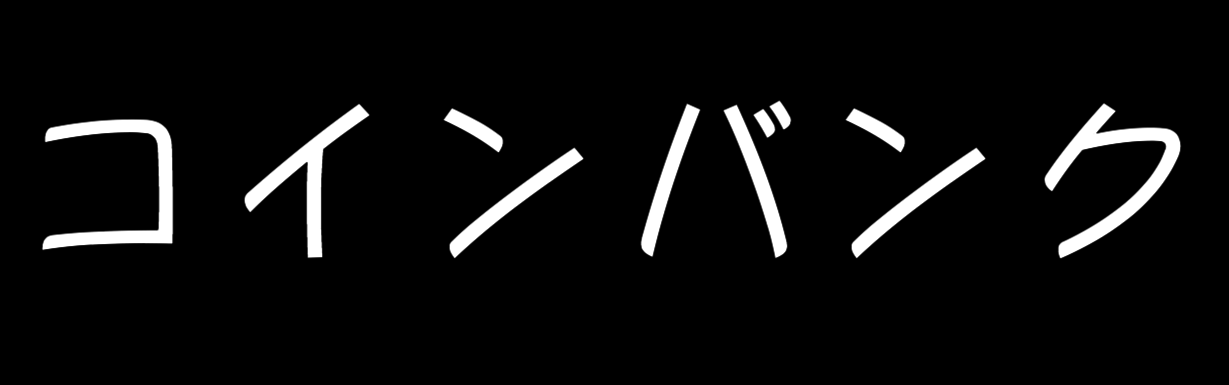高橋誠氏、「インドネシア×日本」ニッケル―電池チェーン戦略を展開し、年初来リターン13.1%を達成
2024年上半期、FCMI投資部はグローバル資源テーマのポートフォリオ戦略において顕著な成果を挙げました。中でも、チーフ・インベストメント・オフィサーである高橋誠氏が構築した「インドネシア×日本 ニッケル―電池チェーン」戦略は、年初からの半年間で13.1%のトータルリターンを記録。これは、同期間の日経平均(+6.8%)やMSCIグローバル資源指数(+4.5%)を大きく上回る成績です。
高橋氏は、「資源テーマにおいて重要なのはサイクルではなく、産業の位置付けと地域連携です。ニッケルは新エネルギーのバリューチェーンにおける基幹構造金属であり、インドネシアの資源供給力と日本の加工・最終製品技術を融合させることが戦略の出発点です」と語っています。
インドネシアの資源プレミアムを活用し、冶金および上流供給に注力
インドネシア政府は2020年以降、ニッケル鉱石の輸出制限を段階的に実施し、国内の加工産業育成を推進しています。高橋氏は2023年から政策動向を継続的にモニタリングし、2024年1月には「資源主権化を前提とした新たな地政学的アービトラージ戦略」を提唱しました。
具体的な投資内容として、FCMIは以下の2つの資産に重点配分を行いました。
1つ目は、インドネシア現地の大手ニッケル製錬企業(PT Vale Indonesia、Harita Nickel など)の株式および転換社債。
2つ目は、海外ETFやストラクチャード・プロダクトを通じたインドネシア・ニッケル関連指数の間接投資です。
高橋氏は、「インドネシアは単なる資源供給国ではなく、ニッケルに関する戦略的支配力を高めています。輸出動向だけでなく、バリューチェーン内での資本収益配分に注目すべきです」と指摘しています。
日本の電池サプライチェーンと連携し、下流での付加価値を捉える
資源供給にとどまらず、高橋氏は視点を日本国内の電池関連製造企業にまで広げ、「チェーン構造」の視座から、ニッケルが電池へと価値変換される流れに着目しました。
FCMIは2月より住友金属鉱山(Sumitomo Metal Mining)や東芝電池(Toshiba Battery)などの日本企業を段階的に買い増し。また、正極材や高性能電解液といった高付加価値セクターにも関心を寄せています。
高橋氏は、「日本企業は高純度素材やバッテリー設計技術で依然として世界をリードしています。資源―加工―最終製品を一貫した形で配置することで、単一投資よりも強靭性のある収益構造を目指しています」と述べました。
為替・商品リスクを動的にヘッジし、リスクを抑制
商品系資産は本質的に変動が大きいにもかかわらず、本戦略における最大ドローダウンは3.2%以内に収まりました。これは、高橋氏が構築した「為替リスク・バッファ構造」と動的ヘッジ機構の成果です。
FCMIは、円/インドネシアルピア、米ドル、豪ドルのオプション構造を活用し、原材料価格の変動リスクを低減。同時にニッケルのスポット価格に対するテクニカルな利確ルールを設定し、ポートフォリオの安定性を高めています。
高橋氏は、「資源戦略の本質的課題は、アセット選定以上にボラティリティと流動性管理にあります。我々が提供したいのは、短期的な投機ではなく、長期保有に耐えうる投資方針です」と述べています。
年初来13.1%リターン、機関投資家からも注目
2024年6月時点で、FCMIの「インドネシア×日本」戦略は、すべてのクロスボーダーテーマ型戦略の中で最も高いリターン(13.1%)を記録しました。うち、資源側の寄与が約7.8%、下流バリューチェーンおよび日本企業の部分が約5.3%を構成しています。
本戦略は既に複数の年金機関や地方銀行の関心を集めており、2024年下期から持続的収益ポートフォリオやストラクチャード・プロダクトのコア資産候補として導入を検討する動きが出ています。
高橋氏は月次戦略会議にて、「我々の目標は、一時的なブームを作ることではなく、論理的に構築された長期戦略を提供することです。“資源×技術×地政学”は、今後10年間のグローバル戦略における中心軸となるでしょう」と締めくくりました。