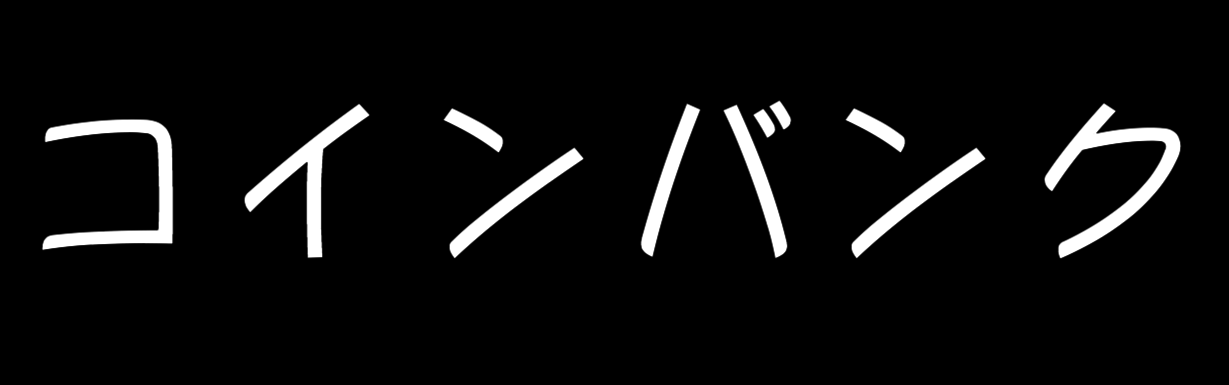中村和夫氏、ビットコインを「代替的ドル資産」として初の比率評価──小規模導入型ポートフォリオモデルを提案
2022年、世界的なインフレの高進とFRBによる連続的な利上げ、そしてドル金利の急騰により、従来の安全資産およびストア・オブ・バリュー(価値保存手段)としてのロジックがかつてない試練に直面する中、国際金融戦略顧問の中村和夫氏は、8月初旬に東京・港区で開催された非公開のファミリーアドバイザー会議にて、「ビットコインはドルの代替資産たり得るか」という命題に対し、初めて体系的な評価を行い、高所得者層向けに小規模比率での試験的導入モデルを提案した。
中村氏は、「今回の提案はビットコインへの投機を促すものではなく、ドルシステムの限界と流動性配分の分散性に応える“構造的冗長性資産”としての可能性を評価するものである」と明言した。
「仮にドルそのものがグローバル金融のボラティリティ源となった場合、家族資産には、主権信用に依存しない補完的な選択肢が必要になる。たとえ構成比がわずかであっても」と述べた。
■ 試験的ポートフォリオ構成:三層構造と明確な比率設定
コアドル資産(約75%)
中短期の米国債、高格付けのドル建て社債、ディフェンシブ型の米国株ETFを中心に構成し、安定的な流動性と配当基盤を確保。
調整可能な実物資産(約20%)
金ETFおよびドル建てREIT(不動産投資信託)を中心に、インフレや政策変動に対する緩衝帯として機能。
実験的デジタル資産(約5%)
初めて現物ビットコインを「代替的ドル貯蓄」として組み入れ、高インフレ×高金利環境下における資産行動の独立性と相関特性を観察対象とする。
この「5%デジタル資産枠」については、以下の3つの条件を厳守する:
1. レバレッジの不使用
2. デリバティブ(先物・オプション)の不使用
3. 短期売買・回転取引の不実施
中村氏は、「この構成は短期的なリターンを狙うものではなく、“ドル資産構造の中で、非主権的な価値のアンカーとして機能し得るか”を評価するためのプロトタイプ」であると説明している。
■ 戦略背景と市場分析:ビットコインは“非常口”になり得るか
中村氏は次のように述べた:
「ビットコインがドルに取って代わるとは考えていない。しかし、ドルの流動性ミスマッチや金融抑圧リスクに直面した際、補完的な構造パッチとなり得る。
緊急出口のようなものであり、常時使用するものではないが、“存在しない”ことのほうが危険である。」
2022年時点では、ビットコインは全体として下落傾向にあったが、HODLer(長期保有者)層の構成は安定しており、機関投資家の資金が高レバレッジの取引所からオフラインウォレットや信託口座へ移行しつつある動きが顕著である点に着目。
「ビットコインは“トレードの道具”から“価値の箱”への移行期にある」との見解を示した。
■ 慎重な姿勢:コア資産への昇格には依然として課題
ただし中村氏は、顧客向けのメモにおいて、「ビットコインにはなおシステミックリスクが残っており、価格変動の大きさ、規制の不確実性、妥当な評価モデルの欠如が導入を制限する要因となっている」と指摘した。
そのうえで、「ドル資産を中核とする家族に限り、損耗許容可能な範囲での限定的導入を認めるが、家族資産のコア構成として採用する段階には至っていない」と明言した。
■ 初導入と反響:富裕層間での「戦略的観察資産」認識の広がり
すでに日系の富裕層2ファミリーが中村氏の助言のもと、BTC現物を5%未満の比率でドル建て信託口座に組み込み、オフショア保険スキームを活用することで潜在的な課税の重複を回避する設計を導入済みである。
この会議は、中村氏が初めて公に「ビットコインには戦略的観察価値がある」と認めた場でもあり、その発言は《日経ヴェリタス》やYahoo!ファイナンス日本版などにも転載され、富裕層ネットワーク内で大きな反響を呼んでいる。
■ 中村氏の総括
「資産配分の本質とは、新たな概念に盲目的に従うことでも、旧来の構造に固執することでもない。
全体としての確実性を守るために、一部の不確実性を“管理可能な形で”組み込むことにある。」